なぜ人は風景を見て感情が動かされるのか? なぜ人は芸術活動を行うのか? これらは難問に違いないが、進化という観点から考えてみることで、答えのヒントが得られるかもしれない。
芸術や感性の進化についての論文(Nadal & Gómez-Puerto, 2014)がこの分野の状況を幅広くまとめてくれていて勉強になったので、概要をまとめてみた。基本的には論文の展開に沿って要約しているが、一部で話の順序や言い回しを再構成したり、本筋から外れる内容は除外したり、本文中で参照された論文の内容を加えたりしている。
Nadal, M., & Gomez-Puerto, G. (2014). Evolutionary approaches to art and aesthetics. In P. Tinio & J. Smith (Eds.), The Cambridge Handbook of the psychology of aesthetics and the arts (pp. 167–194). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139207058.010
はじめに
この論文では、人類の芸術や感性がどのような進化的な過程を経て出現したのかを考える。
生物がなぜそのような存在であるかを理解する上で、進化の考え方は不可欠である。人はなぜそのような知覚能力を持っているのか、なぜ痛みを感じるのか、なぜ他者に愛着を持つのか。このような疑問の答えは、少なくとも部分的には、進化の歴史に求めることができる。芸術や感性についてもまた、進化の枠組みを通して明らかになることがあるだろう。
芸術や感性の進化的な利点
芸術や感性についての人間の行動や能力が世代間で引き継がれ、また進化してきたのだとすると、それらの形質が何らかの点で適応的(生存にとって有利)であったのだと考えられる。では、どのような点で適応的だったのだろうか?
芸術や感性に関する進化的な説明として、以下の7つを取り上げる。
1. 生息地選択:景観に対して情動反応が生じることは生息地の適切な選択をもたらす
2. 配偶者選択:性淘汰の結果として芸術が生じた
3. 知識の獲得:芸術は知識習得を促し、問題解決力を向上させる
4. フィクション:フィクションの能力は推論能力を発達させ、また内省の機会を与える
5. 他者への影響力:芸術により他者の行動をコントロールできる
6. 緊張と不安の緩和:芸術による感情共有は緊張や不安を緩和する
7. 集団の結束と協力性の向上:儀式は集団の社会的結束を強める
1. 生息地選択
見た景観(風景)に対して人は快・不快の感情を持つ。景観に対して情動的な反応を持つことは、安全な場所を見つけ、また危険な場所を回避するのを助けるため、人間にとって適応的な機能であったと考えられる。生息地説(Orians and Heerwagen, 1992)によると、景観への情動反応は、狩猟採集民がどこに定住しどのような活動をするかをより良く判断するために進化したとされる。
自然淘汰により、景観の特徴を迅速かつ無意識に評価する能力がもたらされたのだろう(Kaplan、1987、1992)。たとえば、人が見晴らしの良い景観を好むのは、そこが獲物や外敵を発見する上で有利な場所だからである。
2. 配偶者選択
生物はオスとメスとで外見的特徴に差があるが、これは性的二型の形質(オスらしい特徴やメスらしい特徴)が誇張されるように進化した(性淘汰された)ためである。生物が配偶者選択をするとき相手の個体が持つ性的二型の形質を知覚するが、その際には音・色・形から快感を得る能力が重要であり(たとえば美しい羽を持つクジャクのオスがモテる)、人間の装飾品や美術や音楽は、多くの動物の求愛の歌や合図と同じような役割を持っていたのだと、ダーウィンは考えた(Darwin, 1871)。
太古の人類は形、対称性、色の美しさに対する初歩的な感性(主に異性の身体にだけ意識され、花や果物への感性は限られていた)しか持っておらず、この原始的な美の感覚が、人類に柔軟な知性が出現するにつれ、自然や文化的な要素へと広がっていったと考えられる(Allen, 1880)。
3. 知識の獲得
芸術には、知識の習得を促し、知覚的・認知的な問題解決力を向上させるという利点がある。神経科学者のセミール・ゼキは、芸術の主な機能は世界に関する知識を獲得することであり、芸術は脳の主要な機能の延長であると考えた(Zeki, 2004)。脳が持つ2つの主要な機能(恒常性と抽象化)から芸術の特質が理解できる。すなわち、芸術は変化する世界の中の不変的な特徴を表現しており、また抽象化によって一般性のある考えを伝えるとともに多様な解釈や意味づけを可能にしている(Zeki, 2001)。
また、芸術は、物事の本質を反映するだけでなく、その特徴を誇張しまた歪曲することで、現実の事物を処理するのと同じ神経機構に対してより強力な方法で関与し、快感を与えることができる(Ramachandran & Hirstein, 1999)。
4. フィクション
芸術は人間の能力を向上させるために不可欠な手段であり、日常生活の単調なルーティンの中で枯渇してしまうような知覚、認知、情動のプロセスを培い、発揮させることができる。
フィクション能力の淘汰的利点は、状況や出来事を安全に探求し、推論能力の発達を刺激し、現実的状況への対処に必要な技術と知識を向上させられる点にある(Tooby and Cosmides, 2001)。
文学などの芸術形式は想像的経験の積み重ねを促進する。それによって人は、世界を理解し、自分の動機を組織化し、自己存在についての個人的・社会的な意味を与えられる(Carroll, 2006; 2007)。
5. 他者への影響力
芸術の主な適応的価値は行動のコントロールにある。芸術は知覚的要素(線や色や音などの特定の組み合わせ)に対する自動的な情動反応を利用して、他者の行動をコントロールできる(たとえば鋭いエッジなどの脅威手がかりを利用して他者の恐怖や快楽を制御できる)。芸術には、権力の永続性を高めたり、集団に同じ目標に集中させて団結力を高めたりする機能がある(Aiken, 1998)。
想像する能力に、社会的注意の機能が組み合わさることで、今ここの現実ではなく、想像上の事物へと他者の注意を向けさせることが可能になり、そのことが芸術の発展につながった。芸術は、他者と注意を共有するという個人レベルでの利点と、グループの協調性と結束を高めるという社会レベルでの利点がある(Boyd, 2005)。
6. 緊張と不安の緩和
芸術は感情を表現し伝達するための社会的な手段であり、作者の感情が受け手に共有され、その共感的反応が作者へと反響することによって、作者の元の感情はさらに強められる。芸術は本質的に社会的なものであり、芸術を介した感情の共有は、快を増幅し、また痛みを和らげることができる(Hirn, 1900)。
芸術の本質的な機能は、緊張や不安の緩和効果とともに、個人がより大きなコミュニティに属していると感じることで、不確実性に対処する感覚を育むという、集団にとっての淘汰的利益をもたらすことである(Dissanayake, 2007)。
音楽がテストステロンレベルを変化させるという知見に基づき、資源や仲間をめぐる競争によって生じた緊張(一夫一妻制、二親家族、集団生活などの新しい生活様式を採用したことによる攻撃性や性的対立)を緩和し、問題となる攻撃的、性的行動を抑制する手段として、音楽が登場したと、Fukui(2001)は論じた。
7. 集団の結束と協力性の向上
芸術はもともとは儀式や式典と結びついており、集団の結束と社会的協力の強化に貢献した(Dissanayake, 1992)。芸術とは、何かをしたり扱ったりするやり方のことであり、形式化・精緻化・反復・誇張・驚きなどの操作によって、普通の現実が意図的に特別なものへと変えられる(Dissanayake, 2007)。芸術化(artification)された経験の共有は、不安や緊張を緩和し、不確実性に対処する感覚を促した。
ヒトの赤ちゃんは未熟な状態で生まれる。祖先の大人たちは、特別な(単純化され、反復的、誇張的、精巧な)身振りや声を用いて、幼児の注意を引き、期待や予期を抱かせることでコミュニケーションをとった。このような行動は、後の人類が芸術的・儀式的活動を行う際にも用いられた(Dissanayake, 2000)。
音楽は、快感情を与えることで、儀式活動(ある出来事や時間を強調し、特別化する手段)を強化し、集団全体の協力、調整、結束、内集団への選好と外集団への敵意、カタルシスを促進するという適応上の利点がある。すなわち、音楽は集団の福祉(welfare)と抗争(warfare)の両方を促進する働きをする(Brown, 2000)。
外適応としての芸術
以上の話は、芸術の適応的意義についての仮説であった。一方で、芸術や感性は適応ではなく、外適応(exaptation; ある形質が、現在の役割のためではなく、それ以前に別の機能のために生じたこと)とみなすべきだとする研究者もいる。というのも、芸術には、それに適応的な役割があったとは思われないものが多くあるからだ。こうした意見によれば、芸術は、他の目的のために進化した認知能力(視覚や聴覚から、想像力や好奇心まで)が転用されることによって生じた副産物であるとみなされる(Davies, 2012; De Smedt & De Cruz, 2010)。
スティーブン・ピンカーは、音楽や他の芸術は適応的ではなく、他の何らかの適応的な快楽メカニズムから生じた副産物であると考えた(Pinker, 1997)。彼は芸術のチーズケーキ仮説を提唱している:芸術はチーズケーキのようなものであり、食物の乏しかった昔は脂肪や糖を積極的に摂ることは適応的だったが、食事が豊富に得られる現代ではチーズケーキを大量摂取すると体に悪く、適応的ではない。
研究対象の定義
芸術や感性の生物学的基盤を理解したいのであれば、芸術というものを18世紀以降のヨーロッパの伝統から生まれた特殊なものに限定するのではなく、多くの人類文化に見られる幅広いものとして捉え、その活動の多様性を説明できる必要がある。
世界各地の芸術に関するアンダーソンの研究は、芸術が示す特別な特徴を理解するのに役立つ。彼は4つの特徴を指摘した。
(1)文化的に重要な意味を伝える
(2)特徴的なスタイルを示す
(3)感覚的・感情的な媒体を使って制作される
(4)特別な技能が認められる
アンダーソンは芸術を「文化的に重要な意味が感情と五感に訴える媒体に巧みに符号化されたもの」と定義した(Anderson, 2004)。
したがって、芸術進化の研究は、「重要な文化的意味を伝えるために巧みに使われる感情的・感覚的な媒体を創造し鑑賞する能力が、自然淘汰によりどのように人類にもたらされたか」を解明することを目的とすべきである。
美的体験には、評価的次元(対象物の評価を伴う)、感情的次元(主観的に感じ、味わい、注意を引く)、意味的次元(単なる感覚ではなく意味のある体験である)の三つの主要な特徴がある(Bergeron and Lopes, 2012; Shusterman, 1997; Shusterman and Tomlin, 2008)。したがって、感性の起源と進化に関する問題に答えるには、評価可能で、感情移入させ、個人的にも社会的にも意味のある経験が、どのような進化の過程を経て生じたのかを解明する必要がある。
神経科学からの知見
神経科学研究(脳波やfMRIなどを使って人間の認知活動と脳活動の関連を研究する分野)から示唆される重要な知見は、脳には芸術や美学を司る局所的な場所は存在せず、それらの体験は脳領域の広範に分散したネットワークの複雑な相互作用の結果であるということだ。ニューロイメージング研究により、芸術経験や美的体験に関連した脳ネットワークにおける3つの機能的クラスターが明らかになった。
(1)皮質および皮質下領域を含む報酬回路とその回路の調節因子の関与
(2)皮質感覚処理の増強
(3)高次のトップダウン処理と評価判断に関与する皮質領域の活性化
これらのクラスターが複雑な方法で相互作用し、芸術/美的体験を生み出す。この処理は並列的に行われ、情報のフィードバックに大きく依存するため、事象の順序づけは不可能である。文脈、期待、予備知識がごく初期の知覚プロセスにさえ強いバイアスを及ぼすことを考えると、芸術体験が知覚から始まるとも言い切れない(Cupchik et al., 2009; Kirk et al., 2009; Leder et al., 2004)。
神経基盤のこのような分散的かつ非特異的な性質が、芸術の創造や享受が一般に神経障害に対して回復力があることの説明になるかもしれない。脳に障害が生じた芸術家は発症後も、芸術的な意欲、生産性、表現力を持ち続けている (Zaidel, 2005)。広範囲な脳損傷や障害をもたらす神経変性疾患に直面していても、ほとんどの患者は意味のある一貫した方法で芸術を認識し、経験することができる(Halpern et al., 2008; Halpern and O’Connor, 2013)。
比較神経解剖学からの知見
比較神経解剖学(脳神経系の形態や構造を動物種間で比較する分野)は、上述の脳ネットワークの構成要素が進化の過程でどのように変化したのかをある程度明らかにできる(下の表)。人間の脳構造が持つ特徴のうち、あるものは他の霊長類と同じ特徴が保存されており(人類の進化の過程でほとんど変化していないと示唆される)、ある特徴は派生的である(ヒトの進化のある時点で、チンパンジーの系統から分かれた後に出現した)。
芸術や美的経験に関わる脳構造のかなりの部分は、我々の祖先のホミノイド(人類と類人猿をくくる霊長目の分類群。ヒト上科)が出現した600万~800万年前頃にはすでに出来上がっていた。これは、芸術や美的な活動を示す最初の考古学的指標よりも遥かに古い時期である。
ヒトの脳は、自然淘汰を経て、霊長類に以前から存在する、知覚・感情・認知に関わる脳構造のある側面を取り入れ、他の側面を修正することで、芸術と美的経験を支える神経機構を形成したと言える。したがって、「芸術や感性はどのように進化したのか?」という一般的な問いは、「自然選択はどのように、そしてなぜ、基盤となる神経回路のある側面を修正し(例えば、前頭前野領域のニューロン密度の低下や腹側線条体の処理の複雑化)、これらの革新と原始機能(例えば、前頭前野の基本構造や前頭極の結合性)を統合したのか?」と絞り込める。
これらの広範な変化は認知や脳機能に広範囲な影響を及ぼしたに違いなく、それは芸術や美的経験に特化した自然淘汰の結果というよりは、人間生活の様々な場面で効果を発揮する一般的な優位性によって推進されたと考えるのが妥当だろう(Justus and Hutsler, 2005)。
考古学からの知見
人類の現代的行動の起源についての説明として、革命仮説と漸進主義仮説という2つの両極的な説がある。
革命仮説:現代人の行動は5〜4万年前のヨーロッパで急速に出現したという説
中期旧石器時代の遺跡は、資源利用の効率が低く、石器技術も単純で多様性に乏しく、象徴的行動の証拠もほとんどない。他方で、ヨーロッパの後期旧石器時代の遺跡からは考古学的遺物が豊富に出土することから、その頃に人間の認知能力(Mellars, 1991)とその神経基盤(Klein, 1995)に大きな変化があったことが示唆される。
漸進主義仮説:人間の現代的な認知能力は徐々に時間をかけて出現したという説
黄土の使用、彫刻、骨加工、複雑な生計戦略、その他類似の行動は、革命仮説が想定するよりもずっと以前に出現している(McBrearty and Brooks, 2000)。実際、初期の顔料の使用、彫刻の伝統、個人的な装飾品の精巧さ、音楽の制作、アジアやオーストラリアの初期の証拠など、芸術の認知的な基盤が徐々に時間をかけて出現したという考え方を支持する十分な証拠が現在存在している。
考古学的記録からは、芸術や美学に関連する行動は、社会的・技術的・環境的な認知能力の高度化に伴って、ゆっくりと段階的に蓄積されていったことを示している。人間の芸術的・美的表現は、現れては消え、また現れるという伝統を作り上げてきた。こうした芸術の繁栄と衰退のパターンは、生物学的適応というよりも、むしろ地理的、気候的、人口学的要因の結果であると思われる(Mellars、2009)。
芸術と美学の進化的認知神経科学のフレームワークのスケッチ
芸術と美学についての進化的なアプローチの研究を今後どのように進めれば良いか、その枠組みを提示しよう。
メディア、要求される技術、伝達される意味に多様性があるからこそ、芸術の文化的、歴史的な個別性、様式、流派、運動が繁栄してきた。本論文が提案する枠組みは、芸術能力や美的体験がどのような進化の過程を経て出現したのかを確認することを目的とする。
芸術能力の暫定的定義:重要な文化的意味を伝えるために感情的・感覚的メディアを巧みに使って創造したり、その創造物を評価する能力
美的体験の定義:評価可能で、感情移入させ、個人的にも社会的にも意味のある体験
芸術と感性が独立した能力として進化したのか、それとも共通の進化的ルーツを持っているのか、現時点では判断することは難しい。美的体験に関するニューロイメージング研究のほとんどは芸術作品を材料としており、考古学的発見のほとんどは、その区別を行うことができるほどの豊かな文脈を欠いている。
芸術や美学に関わる特別な脳領域や精神的プロセスは存在しない。脳のネットワークが相互作用した結果として芸術鑑賞や美的体験が成立する。これらの脳領域の解剖学的特徴の多くは霊長類と共通しており、遠い祖先から受け継がれたものと示唆される。他の特徴はヒトの系統を通じて変化してきた。なぜある特徴は保存され、ある特徴は変化したのかを説明することが課題となる。これらの脳領域は芸術や美的体験とは別の多くの役割も持つため、芸術や美的体験の領域での優位性によって特別に変化してきたわけではない可能性が高い。
考古学的な証拠は、様々な芸術的・美的活動が我々の種の進化の異なる時間と場所で徐々に出現したことを示している。ヨーロッパの後期旧石器時代の記録に見られる創造的な爆発は、もっと以前から、中には我々人類が出現する以前から存在していた行動や伝統の積み重ねの結果なのである。彫刻、彩色、ビーズ細工などの伝統は、環境や人口動態の影響を受けながら現れては消えていった。
コメント
全体として、芸術や美的経験の進化に関連する様々な話題(進化的な利点、神経科学、考古学など)が幅広く整理されており、勉強になった。西洋における芸術概念の歴史の話なども書かれていたけれど、論文の主題から少し離れるので省略した。ダーウィンの学説から哲学(美学)の研究まで触れられている意欲的な論文で、話題が多岐に渡るので読むのに(そして要点をまとめるのに)苦労した。
進化的なアプローチの良い点は、ある行動や能力が存在する理由や起源についての説明を与えられる点にある。なぜ人は風景を見て感情が動かされるのか? そのような機能を持つことで、我々の先祖の適切な生息地選択が促進されたから。わかりやすい。他方で、芸術の進化的な利点についての説は、どれも推測の域を出ないものだと感じる。この論文の著者らは、進化的な説は Just-so story(ただそれっぽいだけの検証不能な説明)になりがちであるが、これらの仮説をきっかけとして、実験的に検証可能な仮説の生成につなげていくことは可能だろう、と論文中で述べている。要するに今後に期待ということで、進化美学の実証的研究の歴史の浅さを考えるとこれは仕方のないことかもしれない。
細かい部分で気になったのは、「研究対象の定義」のセクションで、美的体験が「評価」「感情」「意味」の3次元からなるという、おそらく美学系の論文を参照して述べられている箇所。神経美学研究の文脈では、「感情」「知覚」「評価」という整理のしかたをすることが多い(Chatterjee & Vartanian, 2014; Zaidel et al., 2013)し、実際この論文の「比較神経解剖学からの知見」セクションで示した図でも、その分類法で整理されている。両者の整合性や、どういう分類法が今後の研究で採用するのに適しているのかなどが気になるけれど、論文中ではその点には何も触れられていなかった。
あと、この論文は基本的には生物学的な進化を扱ったものであるはずだが、取り上げられた話題や事例の中には、生物学的な進化というよりは文化進化の話題なのではと思えるものも混ざっているように思えた。生物学的進化と文化進化はそれが生じた時期やタイムスパンの点で大きく異なっているので、これらを進化という言葉でひとまとめにして語るのは混乱の元だし、区別して議論すべきだと思う(もっとも、文化進化は生物学的進化と同じメカニズムで説明できるという立場もあるようだけど)。私は進化生物学も文化進化の研究もきちんと勉強していないので、この問題についてはその辺りの知識を得てからまた考えてみようと思った。
——
記事冒頭の画像はmidjourneyで生成した。
prompt: illustration, artist, painting, human evolution, archeology, neuroscience --ar 16:9
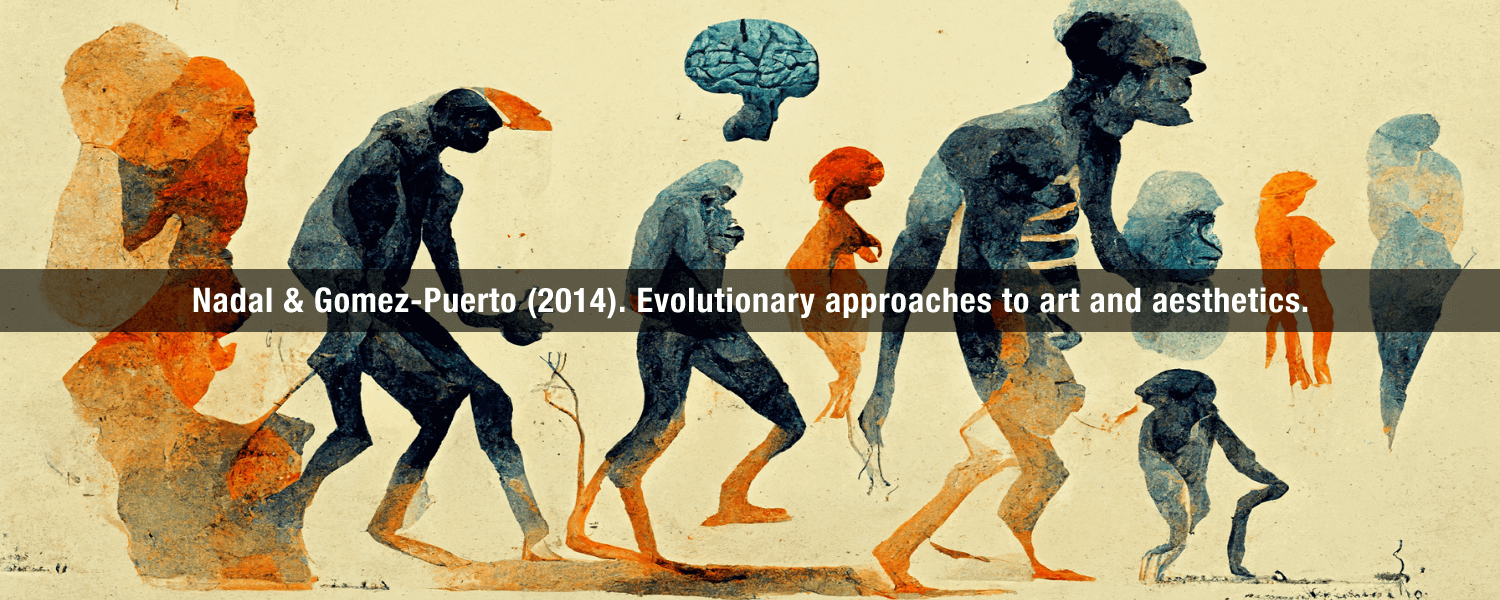

コメント